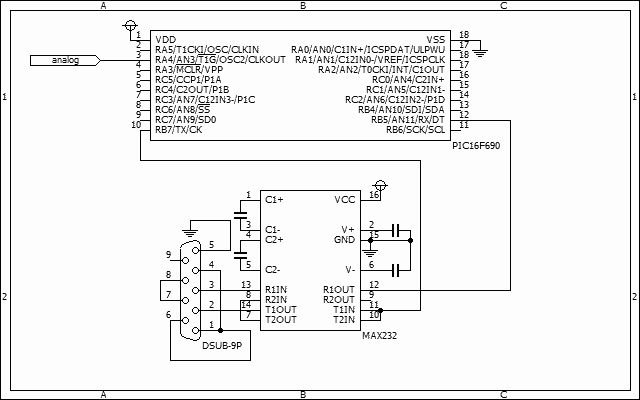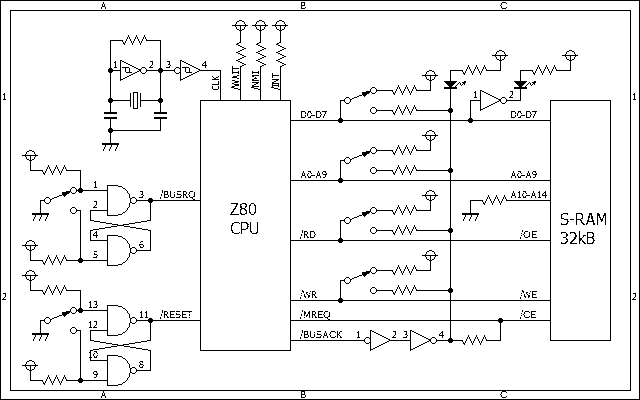IC・トランジスタで出来たコンピューターを設計・製作するためのブログ
| Jeans & Development | 電子ブロック工房 | 三日坊主 | フロントページ |
カセットテープインターフェース [Z80]
2011年11月22日
オシロスコープが動くようになった。本来ならば、このオシロの記事を先に書くべきなのであるが、これを使ってカセットテープインターフェースの回路試作版を作成することが出来たので、こちらを先に。オシロの方は、波形の表示にExcelを使ったりしているので、まだ公表する段階になっていない。こちらについては、また後日。
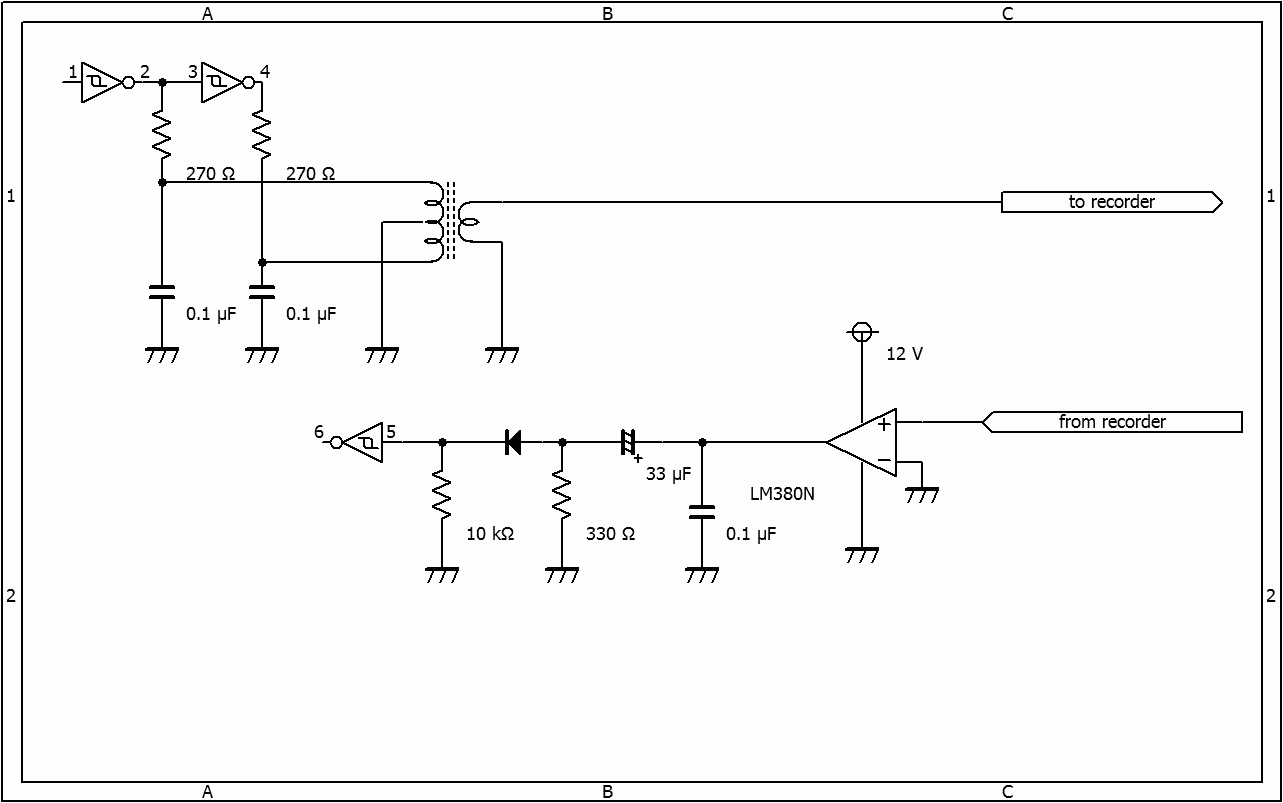
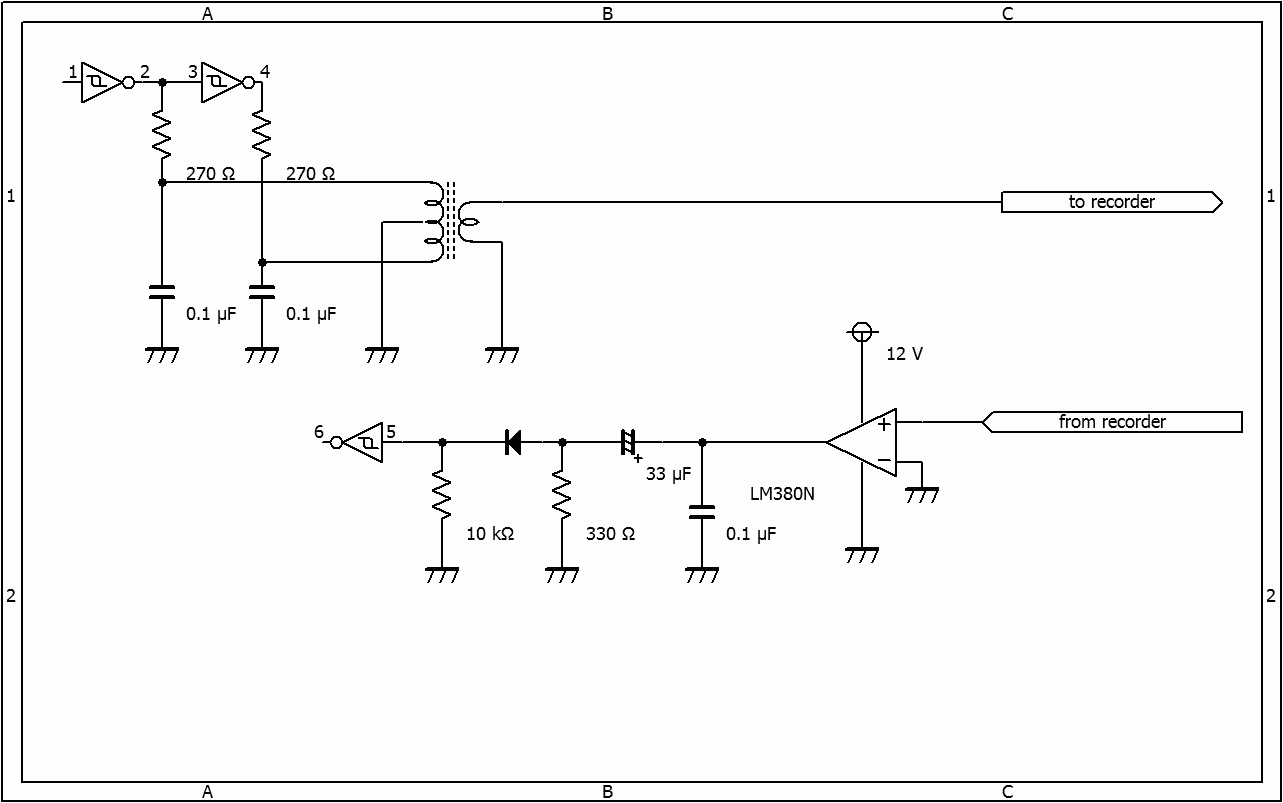
18F14K50で、簡易オシロスコープ その2 [PIC]
2011年11月14日
先の記事で、「家庭用のコンセントの周波数60 Hzを読み取ることが出来た」と書いた。PC側の制御プログラムを完成させようと、この結果を解析してみると、少し問題があることがわかってきた。
まず、PICに1秒間、1ミリ秒当たり24回の測定をさせて、1ミリ秒ごとにデーターを送信させてみた。得られた結果を、Excelでグラフにすると、下のようになった。
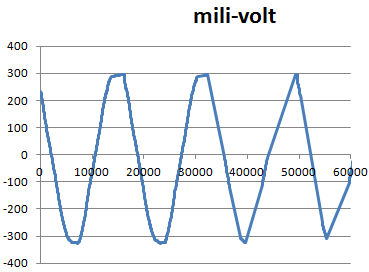
まず、PICに1秒間、1ミリ秒当たり24回の測定をさせて、1ミリ秒ごとにデーターを送信させてみた。得られた結果を、Excelでグラフにすると、下のようになった。
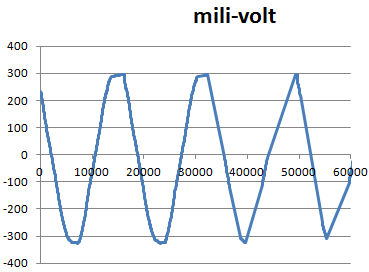
18F14K50で、簡易オシロスコープ [PIC]
2011年11月13日
18F14K50で、USB通信の続き。
先の記事で、とりあえずHIDでの通信ができるようになったと書いた。USBの仕様は膨大かつ複雑であり、これをブラックボックスとして扱わないと、先に進めない。当分の間、この複雑な仕様の部分は「改訂新版 PICで楽しむ USB 機器自作のすすめ」に頼って進めることにする。
HIDでは、一定のタイミングで、PCからPICへ、PICからPCへ、通信が行われているらしい。これは、デスクリプタでもそう宣言しているし、ネットで色々調べてみても、普通はそのような形で行くようだ。
先の記事で、とりあえずHIDでの通信ができるようになったと書いた。USBの仕様は膨大かつ複雑であり、これをブラックボックスとして扱わないと、先に進めない。当分の間、この複雑な仕様の部分は「改訂新版 PICで楽しむ USB 機器自作のすすめ」に頼って進めることにする。
HIDでは、一定のタイミングで、PCからPICへ、PICからPCへ、通信が行われているらしい。これは、デスクリプタでもそう宣言しているし、ネットで色々調べてみても、普通はそのような形で行くようだ。
18F14k50で、USB通信 [PIC]
2011年11月7日
現在、週末はパチパチマイコンのプログラミングで楽しんでいる。16ビットのかけ算ルーチンが完成したので、次は円周率の計算に行こうと、電源を切らずに置いておいた。が、週の半ばで突然の停電。ここカリフォルニアでは、しょっちゅう停電する。為に、プログラミング途中のコードが全部失われてしまった。また一から打ち込まなければならない。
こんな事になる前に、まずカセットテープインターフェースなどの、保存装置が必要だ。もっとも、カセットテープからのデータを読み込むためのプログラムは、電源を切らずにRAMに置いておくか、毎回手打ちするか、この部分はPROMに焼くかをしないといけないのだけれど。
カセットテープインタフェースの回路設計のため、手持ちの部品で、CMOS-ICからの出力をパソコンで録音して、その録音した音をCMOS-ICに認識させるなどのテストを行ったが、どうやらオシロスコープが必要だということが分かった。
オシロスコープも最近は一万円ほどの値段からあるが、今回のインターフェースが完成すれば後は使うことはなくなるかもしれないし、今回の用途は最小限の性能の物で良さそうなので、自作することにした。MicrochipのPICマイコンにはA/Dコンバーターが付いているので、その値を逐次読み取って、PCに送信するだけの簡単な回路で良さそうだ。
そこで、先延ばしになっていた、PCとPICの間を、USBで通信する手法の会得に着手することに。
先日、日本に一時帰国にしたときに、「改訂新版 PICで楽しむ USB 機器自作のすすめ」を買ってある。しかも、パチパチマイコンの部品を購入する際、ついでにPIC18F14k50と、12 MHzの水晶やUSBプラグ差し込み口等も購入してある。お膳立ては出来ている。
こんな事になる前に、まずカセットテープインターフェースなどの、保存装置が必要だ。もっとも、カセットテープからのデータを読み込むためのプログラムは、電源を切らずにRAMに置いておくか、毎回手打ちするか、この部分はPROMに焼くかをしないといけないのだけれど。
カセットテープインタフェースの回路設計のため、手持ちの部品で、CMOS-ICからの出力をパソコンで録音して、その録音した音をCMOS-ICに認識させるなどのテストを行ったが、どうやらオシロスコープが必要だということが分かった。
オシロスコープも最近は一万円ほどの値段からあるが、今回のインターフェースが完成すれば後は使うことはなくなるかもしれないし、今回の用途は最小限の性能の物で良さそうなので、自作することにした。MicrochipのPICマイコンにはA/Dコンバーターが付いているので、その値を逐次読み取って、PCに送信するだけの簡単な回路で良さそうだ。
そこで、先延ばしになっていた、PCとPICの間を、USBで通信する手法の会得に着手することに。
先日、日本に一時帰国にしたときに、「改訂新版 PICで楽しむ USB 機器自作のすすめ」を買ってある。しかも、パチパチマイコンの部品を購入する際、ついでにPIC18F14k50と、12 MHzの水晶やUSBプラグ差し込み口等も購入してある。お膳立ては出来ている。
JavaScript Z80 tiny assembler [Z80]
2011年10月27日
Z80パチパチマイコン用に、簡易なアセンブラーを作成した。HTMLとJavaScriptで出来ているので、どこででも使えるのが特徴。
z80V07.html
z80V08.html
z80v095.html
z80v096.html
スナップショットはこちら。
パチパチマイコンが完成した始めの頃、紙の上でハンドアセンブルしていた。最初のうちはこれも趣があってよかったのだけれど、少し規模の大きいプログラミングだと、アセンブラが欲しくなってくる。作成した物は2進数表示もするので、入力したプログラムの確認が容易にできる。暇を見て、エミュレーターも追加するかもしれない。
z80V08.html
z80v096.html
スナップショットはこちら。
パチパチマイコンが完成した始めの頃、紙の上でハンドアセンブルしていた。最初のうちはこれも趣があってよかったのだけれど、少し規模の大きいプログラミングだと、アセンブラが欲しくなってくる。作成した物は2進数表示もするので、入力したプログラムの確認が容易にできる。暇を見て、エミュレーターも追加するかもしれない。
Verilogを使ってみた [シミュレーション]
2011年7月2日
今の時代、デジタル回路を考える際、HDL (Hardware Description Language)を会得するのは必須のようらしい。FGPAなどの応用範囲もある。覚えておいて損はない、言語だろう。
VHDLとVerilogの両方を試してみたが、Verilogの方が自分には合っているようだ。
VHDLとVerilogの両方を試してみたが、Verilogの方が自分には合っているようだ。
Low Pin Count USB Development Kit [PIC]
2009年10月13日
PICをUSBでPCにつなげたい。日本に住んでいれば、PICで楽しむ USB機器自作のすすめ、この一冊を購入することから始めるのだろうけれど…。
とりあえず、Microchipの『Low Pin Count USB Development Kit』を試してみることにした。
実際にはこのキットは購入していない。購入せずとも、『Low Pin Count USB Development Kit User's Guide』が上記リンクからダウンロードできる。これを読んでみた所、PICkit2があればプログラミングできるようなので、とりあえずPIC18f14k50でのプログラミングがどんなものなのかを体験してみた。
とりあえず、Microchipの『Low Pin Count USB Development Kit』を試してみることにした。
実際にはこのキットは購入していない。購入せずとも、『Low Pin Count USB Development Kit User's Guide』が上記リンクからダウンロードできる。これを読んでみた所、PICkit2があればプログラミングできるようなので、とりあえずPIC18f14k50でのプログラミングがどんなものなのかを体験してみた。
CPU ver 0.0.7.1 [CPU]
2009年10月7日
CPUの規格を、変更。
data line: 8 bits address line: 14 bits (8 bits + 6 bits; 256 x 64; 16K bytes) registors A(8), F(8), PC(12), SP(8) F: Z, C, S5, S4, S3, S2, S1, S0 (Z, C: zero and carry flags; S: segment registor) stack segment is always 0x3f program can be written from 0x0000 to 0x0fff (total 4K bytes) All 2 byte commands 0x00, 0x01, ... , 0x0f: goto, operand: 12 bits. 0x10, 0x11, ... , 0x1f: call, operand: 12 bits. 0x20, 0x21, ... , 0x27: A=A+XX, A=A-XX, A=(XX), [A]=(XX), A=A&XX, A=A|XX, (XX)=A, (XX)=[A] 0x2800 - 0x28ff: A=XX 0x2900 - 0x29ff: stack-using processes bit 0-1: A, reserved, F, or none bit 2: use also c7 for read/write bit 3: SP++ or SP-- at c4 bit 4: SP++ or SP-- at c6 bit 5: SP++ or SP-- at c8 bit 6: 0: SP++, 1: SP-- bit 7: 0: read, 1: write (c5) 0x2900 - 0x2907: A=[SP], reserved, F=[SP], reserved 0x2908 - 0x290f: [SP]=A, reserved, [SP]=F, reserved 0x2910 - 0x2917: pop A, reserved, pop F, SP++ 0x2918 - 0x291f: [++SP]=A, reserved, [++SP]=F, 0x2920 - 0x2927: A=[SP++], reserved, F=[SP++], 0x2928 - 0x292f: [SP++]=A, reserved, [SP++]=F, 0x2930 - 0x2937: A=[++SP++], reserved, F=[++SP++], SP+=2, , , , return 0x2938 - 0x293f: [++SP++]=A, reserved, [++SP++]=F, 0x2960 - 0x2967: A=[SP++++], reserved, F=[SP++++], 0x2968 - 0x296f: [SP++++]=A, reserved, [SP++++]=F, 0x2970 - 0x2977: A=[++SP++++], reserved, F=[++SP++++], SP+=3 0x2978 - 0x2978: [++SP++++]=A, reserved, [++SP++++]=F, 0x2990 - 0x2997: A=[--SP], reserved, F=[--SP], SP-- 0x2998 - 0x299f: [--SP]=A, reserved, [--SP]=F, 0x29a0 - 0x29a7: A=[SP--], reserved, F=[SP--], 0x29a8 - 0x29af: push A, reserved, push F, 0x29b0 - 0x29b7: A=[--SP--], reserved, F=[--SP--], SP-=2 0x29b8 - 0x29bf: [--SP--]=A, reserved, [--SP--]=F, 0x29e0 - 0x29e7: A=[SP----], reserved, F=[SP----], 0x29e8 - 0x29ef: [SP----]=A, reserved, [SP----]=F, 0x29f0 - 0x29f7: A=[--SP----], reserved, F=[--SP----], SP-=3 0x29f8 - 0x29ff: [--SP----]=A, reserved, [--SP----]=F, 0x2a00 - 0x2a03: A=A (NOP), reserved, A=F, A=SP 0x2a04 - 0x2a07: reserved 0x2a08 - 0x2a0b: F=A, reserved, resreved, F=SP 0x2a0c - 0x2a0f: SP=A, reserved, SP=F, reserved 0x2a10 - 0x2aff: reserved 0x2b00 - 0x2dff: reserved 0x2e00 - 0x2eff: (XX)++ 0x2f00 - 0x2fff: (XX)-- 0x30, 0x31, ... , 0x38: A=A+(XX), A=A-(XX), A=A+(XX)+C, A=A-(XX)-C, A=A&(XX), A=A|(XX), A=A^(XX), A=~(XX) 0x39, 0x3a, ... , 0x3f: (XX)=(XX)+A, (XX)=(XX)-A, (XX)=(XX)+A+C, (XX)=(XX)-A-C, (XX)=(XX)&A, (XX)=(XX)|A, (XX)=(XX)^A, (XX)=~A 0x40, 0x41, ... , 0x4f: jz, operand: 12 bits. 0x50, 0x51, ... , 0x5f: jc, operand: 12 bits. 0x60, 0x61, ... , 0x6f: jnz, operand: 12 bits. 0x70, 0x71, ... , 0x7f: jnc, operand: 12 bits. 0x80, 0x81, ... , 0x8f: reserved 0x90, 0x91, ... , 0x9f: reserved 0xa0, 0xa1, ... , 0xaf: reserved 0xb0, 0xb1, ... , 0xbf: reserved 0xc0, 0xc1, ... , 0xcf: reserved 0xd0, 0xd1, ... , 0xdf: reserved 0xe0, 0xe1, ... , 0xef: reserved 0xf0, 0xf1, ... , 0xff: reserved (XX) = [3Fh:XX]; used as registors; genelary, F8-FF (8 registors) are used.
PIC16f690とMAX232でシリアル通信 [PIC]
2009年9月27日
PCとPICとの間で通信ができれば、マイクロコントローラを用いた回路の可能性が広がる。今時のコンピューターでは外部回路との通信にはUSBがメインだが、PIC18f14k50などを用いれば、これができるらしい。他には、FT232Rなどを用いた方法があるようだ。これらの方法は、USB用のドライバを用意する必要があるという点で、少し敷居が高い。少し勉強して、後ほどトライすることにしたい。
今やろうとしているのは、MAX232を用いてRS232Cで通信する方法。今使っているノートパソコンにはRS232Cの端子は無いのだが、USB→RS232C変換機を用いてRS232Cのシリアル通信を行うことができる。
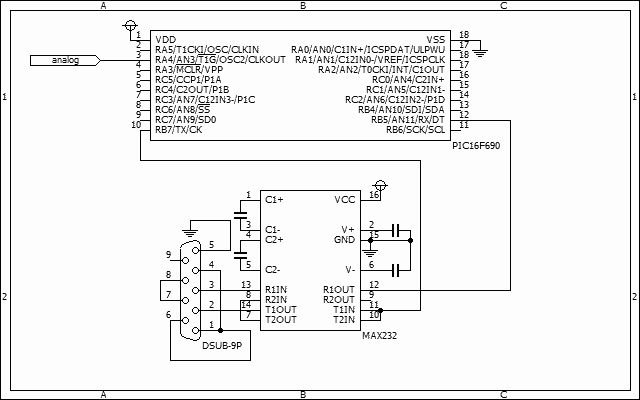
今やろうとしているのは、MAX232を用いてRS232Cで通信する方法。今使っているノートパソコンにはRS232Cの端子は無いのだが、USB→RS232C変換機を用いてRS232Cのシリアル通信を行うことができる。